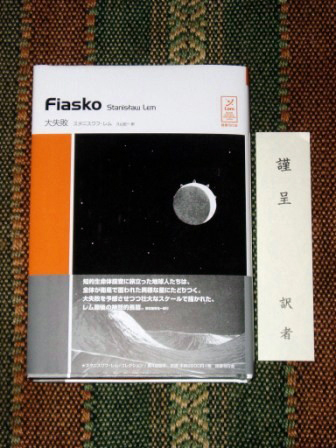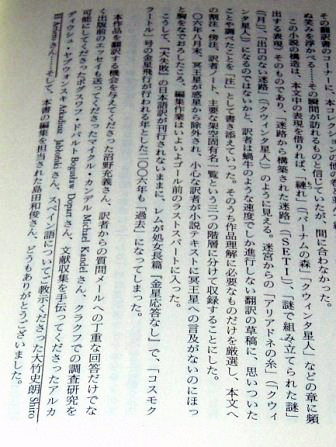今回の日本滞在中、私は仕事をまったくはなれ、軽井沢に三日間滞在しました。
子どもの頃、毎年ひと夏を過ごしたこの美しい土地は私にとって第二の故郷のようなものです。
写真は、30年ぶりに訪れた当時の別荘。私はここで毎日澄んだ空気を吸いながら、自転車を駆って一日中走り回ることによって、現在の丈夫で健康なからだを得られたと思っています。
私はこの木が大好きでした。彼もきっと私をおぼえてくれていたでしょう。
“きみが忘れてしまった故郷の木は いつでもきみをおぼえている
そして夜毎に問いかける 幸せでいるかい それとも...”
子どもの頃過ごした土地との30年ぶりの再会で、私はユパンキの傑作曲、’郷愁の老木’の歌詞を思い出し、いつしか胸をあつくしていました。
shiro のすべての投稿
ヒロシマ・モナム−ル
今回の日本滞在における最初の公式日程が、去る3月17日に広島市に今度新しく発足した「広島スペイン協会」の設立記念セレモニーでのゲスト演奏でした。
午後7時からはじまった懇親会の席で、私はユパンキの「兄弟たち」、ユパンキと、スペインのマヌエル・ベニーテス・カラスコの共作による「微笑みながら坊やは眠る」、そして、私にとってかけがえのないナンバー「ヒロシマ 忘れえぬ町」を演奏。さらにアンコールでは、なにかスペインのものをということで、マヌエル・デ・ファリャの「七つのスペイン民謡」から”エル・パーニョ・モルーノ”のソプラノ・パートをギターの弾き語り(!)にて披露。これは世界でもやる人はかなり少ないはずです。お集りいただいた皆さんはとても珍しいものを聴いていただいたのだと思っています。
東京生まれで現在ニューヨークに暮らす私ですが、ユパンキの詩が縁となって、私を世に出してくれることになった広島は故郷も同然です。
その広島で今回こうしてスペイン協会が発足することになったのは大きな喜びです。
広島スペイン協会の今後のご発展を心よりお祈りいたします。
写真)広島スペイン協会設立記念式典懇親会にて。
El Gran Poeta Granadino
日本へ出発する日が近づいてきました。今回の最初の仕事は、着いてすぐの3月17日に広島で開催される、広島スペイン協会の設立セレモニーへのご招待を受けての演奏です。
当日私は、スペインに縁のあるナンバーを数曲披露するつもりですが、そのなかのひとつとして、アルゼンチンのユパンキと、グラナダが生んだ大詩人、マヌエル・ベニーテス・カラスコ(1922-1999)の共作による「El Niño Duerme Sonriendo – 微笑みながら坊やは眠る」を予定しています。
カラスコの詩作は、日本でほとんど紹介されていないためとても残念ですけれど、現在セビージャの中心地には、彼の名を冠した通り、Avenida Poeta Manuel Benitez Carrascoがあるほどで、やはりグラナダに生まれた、世界的にその名を知られる大詩人、フェデリコ・ガルシーア・ロルカ同様、このカラスコの名はいまもアンダルシアの人々の誇りなのでしょう。
レム最後の神話的長編「大失敗」日本語訳出版に
SF傑作「ソラリス」の著者として、そしてまた「クラクフの賢人」との異名で知られたポーランドの大作家、スタニスワフ・レムの壮大なスケールの長編小説“大失敗-Fiasko”が、日本でとても親しくさせていただいている久山宏一先生の翻訳により、東京の国書刊行会から出版になりました。。
この「大失敗」、ヨーロッパではすでに、英、仏、伊、独、西、露をはじめとする13カ国語によって翻訳出版されていますが、今回、ヨーロッパ以外の言語で翻訳されるのはこれがはじめてであり、この久山先生の功績は、我々日本人にとっても誇らしい快挙といえるでしょう。
実ははずかしながら私も、この本の翻訳段階でほんのちょっとだけお手伝いさせていただきました。
ぜひ多くの皆様に読んでいただきたいと思います。
久山先生がニューヨークに送ってくださった、シンプルでシャープなデザインの「大失敗」。
これから読むのが楽しみです。
私がお手伝いしたのは、第二章に登場するいくつかのスペイン語名称の読み方ですが、それはほんとうに数少ないもので、決して特筆に値するようなことではありません。
しかし久山先生は本文最後のページで、私に対する感謝の意を表してくださったのです。
先生のお人柄がおわかりいただけることでしょう。
素晴らしい本の出版に際して、ほんのすこしでもお役にたてたことをとても嬉しく思っています。
“Radioshow” ON AIR !
1月27日、米国東部時間の午後2時30分、ブエノスアイレスのラジオ局Radio del Plata/の人気番組”Radioshow”のスタッフから、ニューヨークでリハーサル中の私に予定通り電話がかかりました。
まず段取りの説明を受け、しばらくの間、受話器から流れる小気味よいポルテーニョ(ブエノスアイレスっ子)・アクセントによる彼らの放送を楽しんだ後スタンバイのキュー。私の”Zamba del Grillo-こおろぎのサンバ”(目下のところ、私のベスト・ユパンキ・インタープレテーションだと自負)がかけられたあと、司会のレオナルド・グレコとの10分間におよぶ電話インタビューがブエノスアイレスにライヴで流れました。
私とユパンキとの出会い、そしてアルゼンチンとの縁、さらにこれからの活動などのストーリーが、遥かなる距離で南北に隔てられたふたつの魅力あふれる都市をひとつにつなげ、とても充実した、価値のあるいいインタビューになったと思っています。音声も、ブエノスアイレスと話しているとは思えないほどクリアーで、きちんとオーガナイズされた良質の番組でした。
ラスト、私が演奏した「月の踊り」が流される前に、「私たちの音楽を、日本生まれで現在米国にいるあなたが演奏してくれていることをとても感謝しています。」と言われ感激。
私も、「私の人生はアルゼンチンぬきでは考えられません。アルゼンチンのみなさんに感謝します。」と言ってインタビューを終えました。
きっとブエノスアイレスやモンテビデオで聞いてくださった日本人の方々もいらっしゃることでしょう。
いつかまた、声だけではなく皆様とお目にかかれますことを楽しみにしています。
“Radioshow”のプロデューサー、マルティン・フェルナンデスさん、そしてこちらのリハーサルの最中に時間をさいてくださったニューヨーク・サイドの皆さんに感謝をし、文末ながら、Radio del Plataの今後のさらなる発展を祈ります。
(私はこのインタビューでとても大切な二人の人物の名をあげました。私が日本でもっとも尊敬するギタリストの鈴木巌先生と、わたしの人生を語る上で絶対に忘れることの出来ないアルゼンチンのフォルクロリスタ、故エドワルド・マルティネス・グワジャーネスです。今日私は、ブエノスアイレスの皆さんにそのおふたりの名前を知っていただいけたことをとても喜んでいます。)